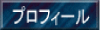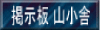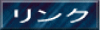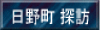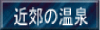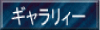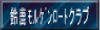トップ
トップ 会員コーナー
会員コーナー
平成26年度の活動
- 綿向山から見える山に登ろうシリーズ(No.27)(2015/3/15/日)
- 平成27年「霧氷まつり」(2015/1/18/日)
- 綿向山から見える山に登ろうシリーズ(No.26)(2014/11/30/日)
- 第14回綿向山清掃登山(2014/5/18/日)
- 平成26年度定期総会開催(2014/5/15/木)
 綿向山から見える山に登ろうシリーズ(No.27)
綿向山から見える山に登ろうシリーズ(No.27)
野坂岳(標高913m)福井県敦賀市
開催日:平成27年3月15日(日)

野坂岳は嶺南に聳え立つ秀峰である。
北陸自動車道を北に進み、敦賀に入ると左にきれいな山容が目に入る。
平重盛がこの若狭にやってきて、この山を見て
「見るたびに富士かとぞ思う野坂山いつも絶やさぬ嶺の白雪」
と歌に詠んでいる。
高さは913メートルと千メートルに及ばない山であるが、その姿はこの歌にあるように富士に似て、市内のどこからもその素晴しさを眺めることができる。
地元の人はここを野坂山と呼び、千日回峰のごとく毎日登っている方もおられると聞く。われわれの綿向山と同じく、古くから山岳信仰の山として、信仰の対象となり、頂上には野坂嶽大権現が祭られている。
今回は11名の参加となり、野坂いこいのキャンプ場の登山口から登った。みんなの陽気さは、前々日までの天気予報と一変した晴天に恵まれたことによる。
途中、青空と雪山と、はるか見下ろせば敦賀市内や常神半島、日本海の景色の素晴らしさが目の法楽となった。
地元の方と思われる登山者と何人かとすれ違ったが、「常連さん」らしく、こだわらない服装とゴム長靴で下って行かれたのが印象的だった。
「この山は霧氷がきれいなのでその時期になると今日は、今日こそは、と期待して登る」とわれわれが綿向山に持っている期待感と同じことを話されていた。
また中には、「綿向山、良く行くよ、霧氷を見に」と言う方もおられた。
野坂山と綿向山が人と霧氷で繋がっている。若狭鵜の瀬の水が東大寺二月堂の若狭井に繋がっているように。
そう思っていると、眼下に原発が見えた。若狭の原発の電気は我々にも供給されている。現在は停止されているが・・・。「鵜の瀬の水」のように、きれいで安全な電気で繋がりたい。
二時間半ほどで頂上に着いた。吹きさらしで風が強いが、展望がよく、東には白銀の峰々が、また、伊吹山や琵琶湖もきれいに見えた。遠くには白山もごく薄らと見えていた。
下山後は時間も早かったこともあり、野坂山を借景にしている江戸時代、豪農の柴田権右衛門の庭園が無料公開されていると言うので見に行った。
富士に似た山容が見事に庭園の主役になって、われわれに迫っていた。
研修部 わたむきやまのグースベリー
(この文章はある作家の文体を真似しています。誰かわかれば心の中でくすっと笑ってください)
 平成27年「霧氷まつり」 平成27年(2015年1月18日)
平成27年「霧氷まつり」 平成27年(2015年1月18日)
今年の参加者は19名でした。
前日降った雪により集合場所の日野町役場でも積雪があり、
西明寺に近づくにつれ、積雪は更に増しました。
メインとなる「霧氷」は、前日降った雪により、霧氷ではなく、雪氷といったところでした。
もう一つのメインの「とん汁」は、頂上は晴天ではないものの、風もきつくなく、
たいへんおいしくいただくことができました。
19名全員、登頂→下山ができました。
みなさまご参加、ご協力ありがとうございました。
写真、アルビレオさん、M山のMさんより


写真、M山のMさん、ラリーベルさん、アルビレオさん、研修部T【画像クリックで拡大表示】


































【画像クリックで拡大表示】
 綿向山から見える山に登ろうシリーズ(No.26)
綿向山から見える山に登ろうシリーズ(No.26)
百里ガ岳(標高931m)高島市朽木
開催日:平成26年11月30日(日)
コース
小入谷登山口→百里新道→シチクレ峠→尾根出会→百里ガ岳山頂→尾根出会→
焼尾地蔵→林道出会→小入谷登山口
小入谷→百里ガ岳山頂 3時間
百里ガ岳山頂→小入谷 3時間
 第14回綿向山清掃登山 平成26年(2014年5月18日)
第14回綿向山清掃登山 平成26年(2014年5月18日)
平成26年5月18日(日)に、恒例となった「綿向山登山道の清掃・整備作業」が予定どおり実施されました。
参加人数は12名と少人数でしたが、当日は好天にも恵まれ、絶好の作業日和でした。
参加者は、午前8時に集合場所である日野町役場に集まり、表参道と小屋の清掃を担当するA班と、水無北尾根コースの登山道整備を担当するB班とに分かれました。
A班は、表参道と3つの小屋の清掃のみならず、五合目小屋ではコンクリートの補修工事を行って小屋を補強しました。
B班は、危険個所が点在する「水無北尾根コース」の登山道整備を何年ぶりかで行うことにより安全性の向上を図りました。
これらの作業が終了後、全員が山頂で昼食をいただきましたが、頂上からの展望が抜群であったことから、一般登山者も含めた登頂者全員に向け横山会長から11月10日の「綿向山の日」と同様、山頂から見える各地の山などの解説をいただき、改めて感激しました。
この後、シャクナゲ尾根を経由して下山しましたが、今年の石楠花は実に見事な花を咲かせており、作業の疲れも吹き飛ぶような心持ちになり、充実した一日となりました。
参加された愛する会の会員の皆様、たいへんご苦労さまでした。


写真、竹村さんよりご提供。【画像クリックで拡大表示】












【画像クリックで拡大表示】
 平成26年度 綿向山を愛する会 定期総会を開催
平成26年度 綿向山を愛する会 定期総会を開催
期日:平成26年5月15日(木)午後8時〜
場所:日野町林業センター
「綿向山を愛する会」の定期総会が開催されました。
総会には18名の出席と65通の委任状が寄せられて会議は成立し、すべての議案が異議なく承認されました。
 ..
..
 ..
..